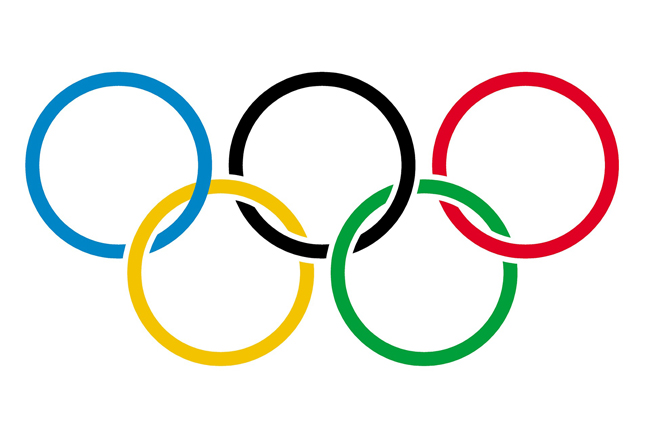視聴率が爆発しない「いだてん」が話題になっているが、よくよく考えてみれば、オリンピック好きと言われる日本人は実はそれほどオリンピックが好きではないのかもしれない。それが、「いだてん」の視聴率と比例しているのではないか?と反省してみる。
実感したのは、オリンピックのチケット抽選が始まった5月9日の10時。ネットを開き登録したIDでアクセス、希望するチケットを求めて、スイスイと行くに及んで、それほど人気がないのかなあ?と思っていたところ、次の段階でもう一つの抽選をしようとしたら、それ以上、動かなくなった。つまりアクセスが殺到し始めたのだ。ニュースでは「締め切りが5月28日なので、慌てる必要はない」との組織委員会のメッセージが出た。
日本人が関心があるのは本番。ところが、先日、新潟に出張した際、バレーボールをやめてそれほど時間が空いてない社会人の女性に「チケット申し込んだ?」って聞くと、「もう申し込むんですか?」そこで、「興味ないの?」って聞くと、「そうですね…」また都内の専門学校2年の女性に聞いても「周りもそんな関心ないみたい」という。
つまり、大会直前にならないと盛り上がらない。なぜ盛り上がるかと言えば、日本人選手が活躍しだして、「血」が騒ぎ出すから。それがきっかけで世界のトップアスリートの活躍にも感動するからということになる。
日本人がオリンピックに燃えるその本質は実はパトリオット(同族意識)であり、オリンピック自身ではない。オリンピズムが主張する「スポーツによる世界平和」あるいは「スポーツを通じた人々の融合」といった理念ではないということである。
オリンピズムを主張する私は、「いだてん」に溢れるオリンピック礼賛思想に感動し、共感するので、「いだてん面白し!」となるのだが、主人公の金栗四三は1912年のストックホルムでのオリンピックでは行方不明になったきりだし、1916年のベルリンは戦争で中止、絶好調なのに勝利の機会も奪われてしまった。となると同族愛も擽られない。
一方、オリンピズムを愛する私は、第19話で役所広司演ずる嘉納治五郎が吐く言葉に感動し、この言葉だけで第19話は完璧と思ってしまうのであった。それは、1920年にアントワープでの五輪開催を国際オリンピック委員会(IOC)が決めた書簡を嘉納が金栗に見せるシーンであった。
「最も被害が大きかったとされるベルギーでこそオリンピックを開く意味があるとベルギーのラトゥール伯爵が手をあげてくれたんだよ」
まさにオリンピズムである。ドイツに占領されたベルギーの被害は相当なものであった。戦争の犠牲となった多くの人々、とりわけベルギーの人たちの勇敢な行為をたたえる意味を込めて大会を実施することを追認したのは、大戦終了後にクーベルタンがIOC委員をローザンヌに呼んで行ったことである。
「いだてん」ではそこをラトゥール伯爵の勇気ある意思にまとめているが、実際は、1914年のIOCの会議で、1920年に第7回大会をすることを決めていた。1916年の第6回大会(ベルリン)が戦争で流れたが、第7回は予定どおり行うというIOCの意思こそ、もっと深くオリンピズムを表すものである。
なぜなら、そこにオリンピックを近代に復興させた意義が端的に表されているからである。ベルリンは戦争で中止されたが、アントワープは戦争を超えるのだ!という意気である。
ラトゥール伯爵が戦禍のアントワープで記者団を前に演説し、それに記者も賛同の拳を上げるシーンは、しかし、感動的であった。そして、嘉納が金栗に「戦争があってもオリンピックを開く!そこに意義があるんだよ」というその場面こそ、今の日本オリンピック委員会の人々に突き刺したい一言である。
「いだてん」の金栗四三は時折「こんどこそお国のために、金メダルをば」と言ったようなセリフを吐くが、このことと日本人がオリンピック大会直前にならないと盛り上がらないの心は同じところにある。そしてこれを金栗がどのように克服していくかを「いだてん」は示すべきだろう。
第二次世界大戦に出兵する人々もそれを送り出す人々も「お国のため!」と言った。しかし、オリンピズムは明らかに国別メダル獲得票を拒否する。オリンピックの名誉は選手個人に帰するからだ。
この矛盾に「いだてん」も常に問いかけを行っているのも見逃せない。肋木にぶら下がる人に嘉納が「面白いか?」と何度も聞く第一話のシーンが思い出されるが、金栗四三が走るのはただ自分のためであるという原点は常に想起されなければならないだろう。
自らが自らの好きなことに懸命になり、そのために心身を鍛え、その闘う姿を人々に問うことで、オリンピックが成立する。そのオリンピックが戦争を超えて、新しい人々の和を作る。個の努力が世界の和につながる。ゆえに金栗四三の走り続けることに意味がある。
そしてここが肝なのだが、金栗四三の言う「お国のため」は、紐解けば、自分勝手な自己実現を支えてくれている綾瀬はるか(妻)であり、大竹しのぶ(義母)である。つまり自分の血周辺である。同様に大会直前に盛り上がっていく日本人気質も血周辺である。
IOC現会長バッハが昨年2018年11月に東京で開かれたANOC総会で演説した。「パトリオティズムは健全な人間の心持ちである。しかしそれがナショナリズムになった時、IOCは黙っていない」私流に言えばオリンピズムはナショナリズムを利用してナショナリズムを超えるのである。
これから「いだてん」がオリンピズムを伝えれば伝えるほど、視聴率が上がると信ずるは我一人か?役所広司にいやいや嘉納治五郎に期待する。
純粋五輪批判第六話了
春日良一